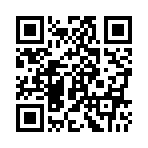昨日は子供の七五三だったので、終わってから少し川歩きしてきました。


今は安里川にいないと思われているターイユ(フナ)。
実はいっぱいいるのですが、上流から下流まで工事が続いて、フナ付き場(?)が変わってしまっています。
さて、フナはどこへ行った?
フナ釣りといえば、主に植物性(または動物性と配合)のネリエサを使い、釣り糸をたらして静かにウキとにらめっこするのが定説なのですが、安里川のフナはルアーでもよく釣れます。つまりは、植物系ではなく動物系のえさも好んでいるということです。
フナは雑食といわれていますが、ミミズなども食べているので、ミミズを模したルアーでも釣れる、ということなんでしょう。
安里川では、上流から下流まで、河川の浚渫工事が行われています。
市街地を流れる川で、沖縄の都市河川特有の鉄砲水や氾濫が心配されているためだとは思いますが、水理に反してフラットにされているところが多いのです。
川のカーブ部分は、外側はえぐれて、内側は堆積物が溜まります。
フラットにすれば、外側の水量が増えて逆に危ないと思うのですが・・・
結局、大雨で元通りの地形になってしまいます。
フナの居場所は、まさにこうした「淵」の部分です。
おそらくは、深い場所は神経質と言われるフナの隠れ家になっていて、カーブの内側の浅い場所に堆積した土砂には、フナが好んでいるミミズなどを育む場所となっているのでしょう。
フナは沖縄で田魚「ターイユ」といわれ、その名のとおり田んぼに住む魚として知られています。
沖縄では「ターイユシンジ(田魚煎じ)」という薬膳料理があって、風邪などのときの滋養強壮によいとされ、親しまれてきた魚でもあります。
昨日、フナをつっている時に話しかけてきたおじさん達も、今も需要があるがフナがいなくなっていて、「まさか安里川にこんな大きいフナがいるとは・・・」と驚いていました。
時々、安里川にフナがいることがわかる目利きの方もいますが、多くの人は身近な魚だった安里川にフナはいないものと思っています。まだまだ汚いの意識ばかりが先行し、勝手にいないものとされちゃうんですね。
昨日釣ったでっぷりしたフナ。
やっぱり淵にいましたよ。
安里川の色々な情報を発信することで、効果的な河川改修に一役買えるといいですよね。
フナがいっぱいいることが広く伝われば、水理や安里川の生態系をもっと考えた、効果的な治水対策を考えてくれることを願います。淵を埋めたために、大雨で余計に氾濫してしまう治水対策って、税金の無駄遣いですからね。